- 子どもが「学校に行きたくない理由がわからない」
- よく分からずモヤっと、学校に行きたくないという気持ちがある
そんな悩みや疑念、昨今ではよくある話かと思います。
何といっても、2010年~2020年代と時代が経つにつれて、
実際俺が学生だった頃よりもさらに価値観の多様化が進んできていますからね~
とりわけ
「旧来型の古い義務教育が多様化する現代に対応できていない」
という事実を踏まえた上で、
今回は
「学校行きたくない問題」
「それでも義務教育は受けるべきなのか」
といったテーマについて考えてみました。
 HATOBA
HATOBAこんにちは。このBlogを書いているHATOBA(はとば)です。
- 名門都立高~国公立大を卒業(※血反吐出そう)
- 社会経験5年以上のエンジニア(※精神的に限界)
- 発達障害に理解あり♪(当事者視点)
学校に行きたくない理由は本人にも不明
子どもが「学校に行きたくない」と言っても、その理由を明確に言葉で表現できないことがあります。
これは、心や体が無意識に学校を拒否しているサインかもしれません。
例えば、
- 朝になるとお腹が痛くなる
- 頭が痛くなる
- よく分からないまま涙が出て泣いてしまう
などの身体症状が現れることがあります。
これらは、心理的なストレスが身体症状として現れている可能性があります。
子ども自身も、なぜ学校に行きたくないのかを理解できていない場合があります。
そのため、親が「理由がわからないのに休むのは甘えだ」と決めつけてしまうと、
子どもをさらに追い詰めてしまうかもしれません。
このような場合、まずは子どもの話に耳を傾け、安心して話せる環境を整えることが大切です。
子どもが自分の気持ちを整理し、言葉にできるようになるまで、焦らずに見守る姿勢が求められます。
義務教育の無意味さ
ここでもっと掘り下げて、そもそもの議論をしましょう。
率直に言って「義務教育のやっていることは無意味である」と、俺は捉えています。
なぜなら義務教育以前に、もっと大枠の「国民国家」そのものが今の時代において、
意味を失い破綻に向かってきているからです。
みなさんは、義務教育というものが世界史上の、いつ頃を発端として始まったかをご存じでしょうか?
歴史的な経緯としては、18世紀にフランス革命が起き、ナポレオン・ボナパルトが台頭していた時期と言われています。
ちょうどこの時期に「国民国家」という、現代のアメリカ・フランス・日本などなど
さまざまな「国家」そのもののモデルの原点が生まれました。


「国民国家」を構成するものは「議会」「官僚組織」
そしてその下地となる「学校」制度です。
この「国民国家」において義務教育が果たしてきた機能というのは、以下の通りです。
- 「国民軍」(軍隊)のメンバーとなる国民(兵士)を権力に服従させ、徴兵し国家に奉仕させる奴隷を養成すること
- 国民国家を運営する官僚組織をつくること
→ おもに成績優秀なエリート達を上位に置いて、指揮命令を上から下に流していく、いわゆる縦型の組織のことですね。
このように、義務教育というのは「国民国家」をつくるための重要な機関として捉えられます。
もともとの歴史的経緯をたどると、友達と楽しく遊んだりする場所ではないということが分かります。
同世代の子ども同士で交流が必要だとおっしゃるのであれば、別に学校である必要はないです。
学校の代わりになる場所は、地域の大人や、行政の力で他にいくらでも作れるはずです。
また義務教育というのは、
「生きるための知識を身に着ける上で不可欠だ」
とおっしゃる方もいると思います。
ですが実際ほとんどの学校やっていることは、お役人が一方的に決めた学習要領に沿って
- 教育の場において詰め込まれる知識が、個人個人の人生にとって必要か・必要でないか
- 個人が勉強したいと興味を持つ内容なのかどうか
といった観点を度外視した、単なる上から下への命令の押しつけであり、
実態としてはやはり、軍隊や官僚組織をつくるための教育です。



義務教育… おもんなくないですか?
「生きるための知識」が何なのかは、義務として上から画一的に与えるのではなく、
個人が決めて個人で身に付けられる形にすればよいのではないでしょうか?
そもそもあなたは国民軍の兵士として戦地へ向かいたいでしょうか?
自分の子どもを兵士として育てたいのでしょうか?
※たとえば「わたしは自衛隊に志願したい」「お国のために戦って死にたい」とか、
そういった願望のある人だけに義務教育を施せばよいのではないでしょうか?
「学校に行きたくない理由がわからない」という疑問をお持ちの方は、まずは自分が思考停止に陥っていることを自覚したうえで、ぜひこのような視点に立って「義務教育」の意義を根本的に捉え直してみてはどうでしょうか?



俺は、学校行かなくて済むならやっぱり、行きたくなかったですねえ~
将来何の役に立つかよくわからん勉強するぐらいならずっと遊んでたいじゃないですか
直感的にも間違ってると思うし、
大人になって振り返ってみても、人生の時間を無駄にスポイルさせられたなという感想しか出ないです
義務教育は意味ないと感じてしまう理由
先ほどと同じ繰り返しになりますが、義務教育はすべての子どもに同じ内容を教えることを目的としており、実際には一人ひとりの個性や興味、学習ペースに合っていないことが多くあります。
例えば、以下のような問題点が指摘されています。
- 一斉授業では、理解が早い子どもも遅い子どもも同じペースで進むため、どちらにとっても不満が生じやすい。
- 評価基準がテストの点数や成績に偏っており、創造性や思考力などの多様な能力が評価されにくい。
- 学校のルールや校則が厳しすぎて、子どもの自由な発想や行動を制限してしまう。
これらの要因から、子どもたちは「学校に行く意味がわからない」「学ぶことが楽しくない」と感じるようになり、結果として学校に行きたくないという気持ちが芽生えることになります。
義務教育のあり方を見直し、子ども一人ひとりの個性や興味を尊重した教育が求められています。
子どもが学校に行きたくないのは自然なこと
子どもが学校に行きたくないと感じることは、決して異常なことではありません。
むしろ、自然な感情の表れと捉えることができます。
現代の学校生活は、以下のような要因で子どもにとって負担となることがあります。
- 友人関係のトラブルやいじめ。
- 授業についていけない、成績が思うように上がらない。
- 先生との相性が合わない。
- 校則やルールが厳しすぎる。
これらの要因が重なることで、子どもは学校に行くこと自体が苦痛になってしまうのです。
そのため、子どもが「学校に行きたくない」と感じるのは、ごく自然な反応と言えるでしょう。
親はそういった子どもの気持ちを否定せず、まずは受け入れることが大切です。
「何がつらいのか」を一緒に考え、解決策を見つけていくことが、子どもの安心感につながります。
義務教育に代わる新しい学びの形
近年、義務教育に代わる新しい学びの形が注目されています。
子ども一人ひとりの個性や興味に合わせた教育方法が求められる風潮があるためです。
以下に、代表的な代替教育の形を紹介します。
- ホームスクーリング:家庭で親が子どもに教育を行う方法。学習内容やペースを自由に設定できるため、子どもの興味や能力に合わせた学びが可能です。
- フリースクール:学校に通えない子どもたちが集まり、自由な雰囲気の中で学ぶ場。人間関係のストレスが少なく、自分のペースで学習できます。
- オンライン学習:インターネットを活用して、自宅で学習する方法。多様な教材や講座があり、子どもの興味に応じた学びが可能です。
またIT技術が画期的な進歩を遂げた今の時代では、世界中の有名大学がオンライン講義を動画配信で実施しています。
語学の勉強さえしっかりやれば、日本で世間的に一流と言われている大学よりさらにレベルの高い講義を低コストで、自宅から受けることも可能になっています。
受験競争を勝ちぬいて将来、有利なポジションを取りたいという動機で学校に通う必要はまったく無いですし、義務教育は子どもが精神的なダメージを受けるだけで、コスパも非常に悪いと言えます。
これらの選択肢を検討することで、子どもにとって最適な学びの環境が何であるか、見つけることができるかもしれません。
親側は、子どもの意見を尊重しながら、柔軟に対応していくことが求められます。
[PR] 累計10万人受講のロボット&プログラミング教室【ヒューマンアカデミージュニア】
楽しく分かりやすくロボット技術やプログラミングを学ぼう!
子ども向け教室のご紹介です。
- 全国2,000教室以上で開講
- ロボット電話「RoBoHoN(ロボホン)」ロボット宇宙飛行士「KIROBO(キロボ)」を開発した一流クリエイター「高橋智隆氏」による教材監修!
- さまざまな分野に応用できる「考える力」、そして理数系の基礎となる「空間認識能力」が楽しく身に付く!
興味ある方はぜひこちらから↓ 体験授業の参加申し込みをしてみてください!
まとめ:「学校に行きたくない」は何らおかしな事ではない
ここまでで以下の悩みや疑念に対して、考え方や歴史的な視点について触れてきました。
- 子どもが「学校に行きたくない理由がわからない」
- よく分からずモヤっと、学校に行きたくないという気持ちがある
結論としては
- そもそも学校には行かなくてよい
- 義務教育の本質はあなた個人のためではなく、国家権力・システムを構築するためのしくみに過ぎない
- いま現在においては、旧世紀の名残りとして惰性で続けられているだけの無意味で不要なものである
ということになります。
子どもが「学校に行きたくない」と感じることは、ひとりの人間の直観としてとても正常な反応です。
子ども自身が自分の気持ちに正直である証拠とも言えます。
親はそういった子どもの気持ちを否定せず、まずは受け入れることが大切です。
その上で、子どもが安心して話せる環境を整え、一緒に解決策を考えていく姿勢が求められます。
また社会全体においては、義務教育のあり方を見直し、子ども一人ひとりの個性や興味を尊重した教育方法を検討する必要があると言えます。
人が自分らしく学び、成長できる環境を得られることがきっと、人類の幸せにつながるだろうと思います。

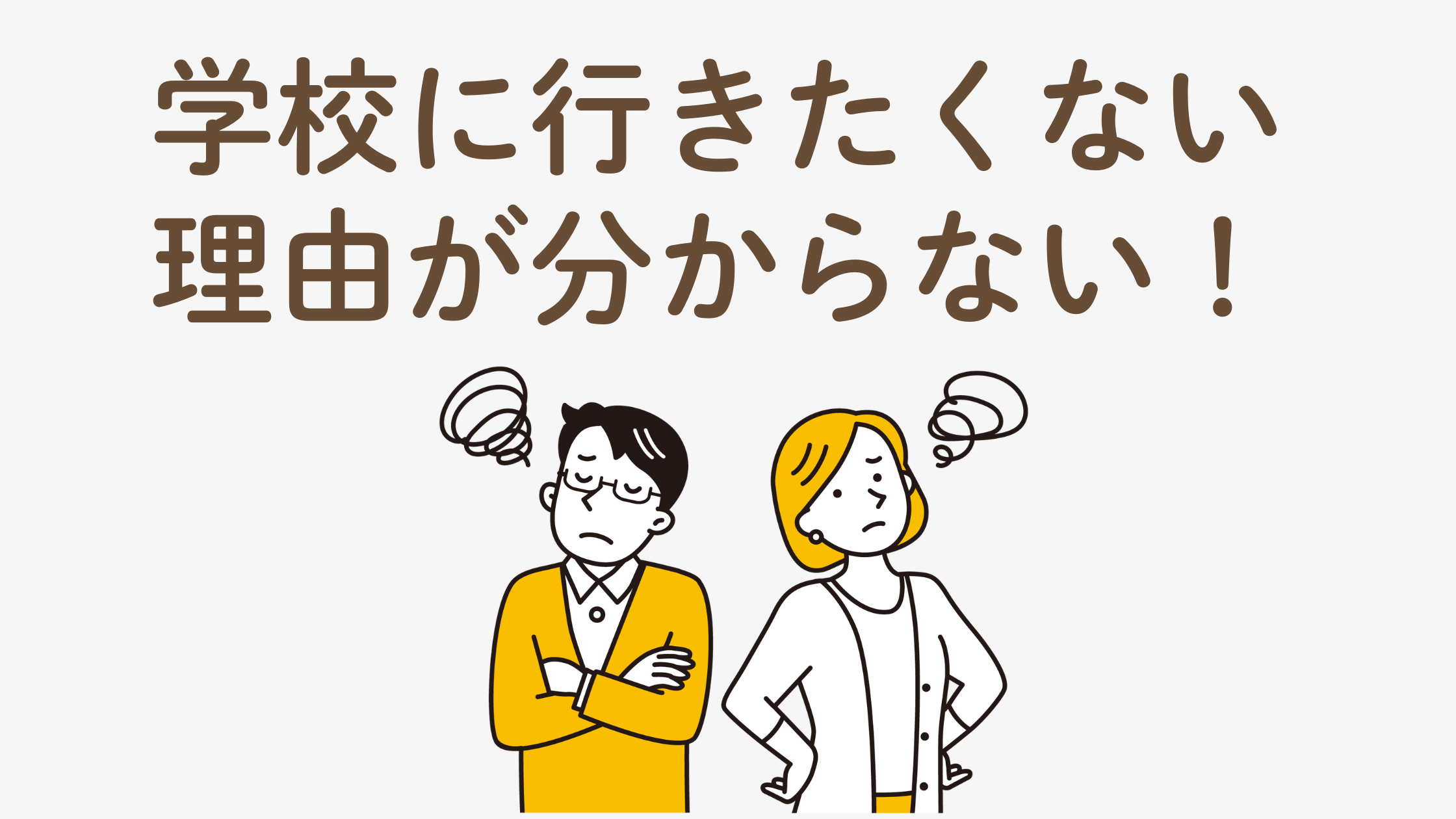

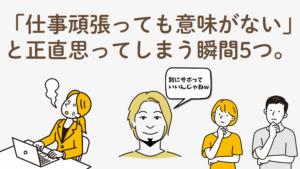
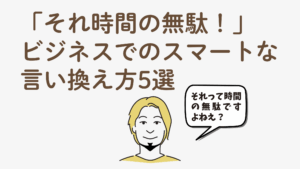
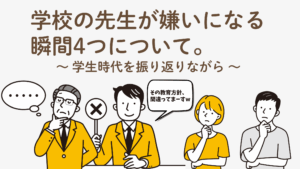
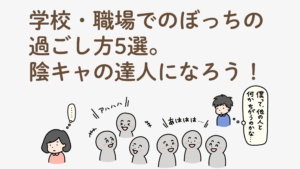
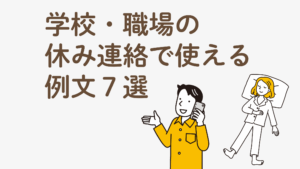
コメント